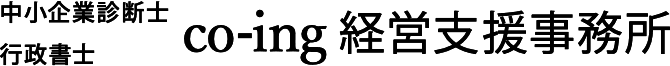建設業の営業は外注か?自社雇用か?中小建設業が考えるべき営業体制戦略
建設業の営業は外注か?自社雇用か?中小建設業が考えるべき営業体制戦略

こんにちは。co-ing経営支援事務所の中小企業診断士・行政書士、倉島悠輔です。
屋根や外壁修繕をはじめとする建設業の経営者からよく相談を受けるテーマのひとつが、**「営業を外注に任せるべきか、それとも自社で社員を雇用すべきか」**という問題です。
どちらも一長一短があり、会社の経営戦略や体制によって最適解は異なります。本記事では、建設業に特化して営業体制を考える際のポイントを整理しました。
営業を外注するメリット・デメリット
メリット
・即戦力を確保できる:営業経験や業界ネットワークを持つ外部人材をすぐに活用できる。
・変動費として扱える:成果報酬型の契約なら、人件費を固定費化せずリスクを抑えられる。
・自社にないスキルを導入できる:マーケティングや新規開拓に強い外注パートナーと組める。
デメリット
・ノウハウが社内に残らない:営業スキルが外部依存になり、将来の自立性を損なう。
・ブランド理解が浅くなる:下請け色が強くなると、自社の強みや理念を顧客に伝えにくい。
・コストが割高になることも:固定報酬+成果報酬型だと、社員雇用以上に費用がかさむ場合もある。
営業を自社雇用するメリット・デメリット
メリット
・ノウハウが蓄積する:営業の仕組みが社内資産として残り、次世代にも継承できる。
・顧客関係を長期的に構築できる:社員だからこそ顧客と深くつながり、信頼を得やすい。
・理念や方針を共有しやすい:経営方針を理解した社員が営業することで一貫性が生まれる。
デメリット
・採用・教育コストが大きい:人材育成には時間と費用がかかる。
・固定費が重くなる:成果が出なくても給与を払い続ける必要がある。
・すぐに結果は出にくい:特に建設業の営業は信頼構築型のため、短期間での成果は難しい。
判断のポイント|建設業ならではの視点
1.顧客ターゲットは誰か?
工務店やハウスメーカーへのBtoB営業か、一般住宅オーナーへのBtoC営業かで最適な体制は変わります。
2.地域密着か、エリア拡大か?
地元紹介中心なら外注より自社社員の方が相性がよく、広域展開なら外注のネットワークを活かす手もあります。
3.資金繰りに余力があるか?
固定費を抱える余裕があるのか、それとも変動費化してリスクを抑えるべきかを検討。
4.将来の戦略は何か?
「下請中心で安定受注を狙う」のか、「直販強化で独自ブランドを築く」のかで方向性は大きく異なります。
ハイブリッドという選択肢も
実際には「外注か雇用か」の二者択一ではなく、ハイブリッド体制が現実的な場合も多いです。
・新規顧客開拓は外注営業に任せ、リピートや紹介顧客は自社社員がフォロー
・立ち上げ期は外注で営業力を補強し、徐々に自社に営業ノウハウを移管する
・デジタル集客は外部パートナーに依頼し、現場訪問やクロージングは自社社員が担当
このように役割分担することで、リスクを抑えながら営業力を高めることができます。
まとめ|営業体制は「経営戦略」の一部
営業を外注するか、自社で雇用するかは、短期的な人手不足の問題ではなく、中長期的な経営戦略の選択です。
「どんな顧客をターゲットにするのか」「今後どんな事業展開をするのか」によって最適な体制は変わります。
もし営業組織の作り方に迷っているなら、まずは経営戦略を整理し、自社の方向性を明確にした上で判断することをおすすめします。
co-ing経営支援事務所では、中小建設業の経営戦略策定から営業体制の設計まで、伴走して支援しています